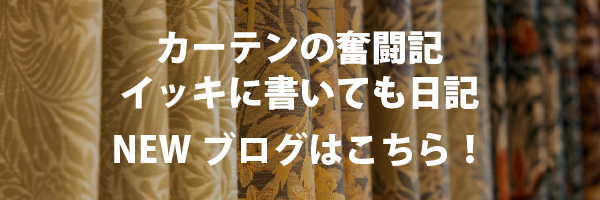人間ドッグに行ってきました。
毎年誕生月に申し込みをして7月頭に行ってまして20年ぐらいのデータが
残っています。
昨年に比べて体重が3キロ減り、身長が1ミリ短くなり、視力が左目だけが
0.1以下で大きく落ちました。(右目は1.0で、老眼鏡は必要としてません。)
正確なデータは未だですが受診後の医師による結果報告では、
すべて正常範囲で問題がないとのことです。
健康優良大人です。
さて、本題です。
ブログにはいいことばかり書かないで失敗した話も書かねばと思っています。
実は失敗話もそこそこありますが、そんな話ばかりになると「この店、
大丈夫かな?」と思われるので、工夫した話も書いておきます。
タワーマンションのコーナーの窓で大きな変形台形窓になっています。
カーブレールが初めからダブルで、天付ブラケットを使ってついて
います。
レースはそのレールを使って1.5倍使いの両開き、ドレープ(厚手カーテン)は
台形の斜めの辺はカーテンで、正面はプレーンシェードにしたいという
要望でした。
そのレールをうまく使うため、ダブルブラケットは残して、手前の
レールの正面部分をカットしました。
引っ越し日で荷物がいっぱいあります。
プレーンシェードがあるところも天付のダブルブラケットが残っていて、
それをかわすためにブラケットスペーサー(樹脂製のかまぼこ板のようなもの)を
入れて、カーテンボックスの天とシェード本体との間に隙間があくように
つけています。
そこで、シェードの幕体にマジックテープをつける位置を従来より
下にして、上部がメカより上ににでるようにして隙間が見えないように
しています。
(画像はクリックすると別のページに飛びまして、そこでもう一度
クリックすると拡大します。)
台形窓は右と左の斜めの辺の長さは違うのですが、レースの巾を
変えて、真ん中の面のど真ん中で両開きがわかれるようにしています。
![]() –
– ![]() –
– ![]() –
– ![]() –
–
このブログのトップへ