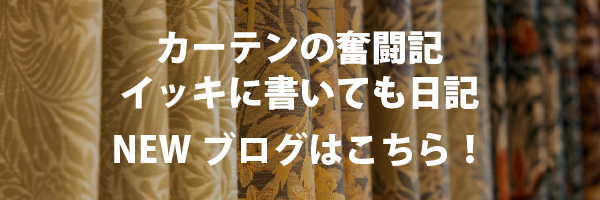最近、このブログのアクセス数が一段と増えてきました。
ブログランキングの評価はひじょうに低くても気にしていませんが、毎日のアクセス数は気になり、この数字が伸びるのが一番の楽しみです。
アクセスが増えている要因はよくわかりません。毎日書いているからかなぁ。
そんなことを考えているとなかなかブログを休めなくて、自分にプレッシャーをかけています。
さて、本題です。
新店舗に移るにあたっていろんなことを考えているのですが、そのひとつにプライスカードの表示をどうするかという問題があります。
ここ20年のオーダーカーテンショップの流れの中で画期的なショップが3つありました。
1つめは昨日のブログに書きました17~18年前に出始めた「カーテンの無料レンタル試着システム」を採用したところです。
2つめは、オーダーカーテンの価格はわかりにくいということで、S,M,Lの3つの価格帯で販売し急激に多店舗展開をしたところです。
3つめはオーダーカーテンの低価格均一ショップで、巾200×丈200センチのサイズを1万円で販売したところです。
2つ目の店は2年前になくなりました。
3つ目の店は7~8年前に出始めまして、業界では1万円ショップもしくは万均ショップと言われているところです。
ここもオーダーカーテンの価格は分かりにくいということで、価格を統一するという形で、200×200センチのサイズならばドレープですべて1万円の商品だけ揃えたのです。
そして巾100~200センチまでならば、丈が腰窓の120センチでも、天井からのカーテンボックスの240センチでも同じ価格にしたのです。
実際は丈120センチと240センチでは使う生地の量は大きく違いまして価格ももちろん違うのですが、販売価格は同じ設定なんです。
最初にやったところがすごい売り上げをしたものだから、多くの店がこのやり方の真似をしてブームになりました。
これってわかりやすいの?
誰がわかりやすいの?
エンドユーザーにとって巾が同じならば腰窓もカーテンボックスからの窓もカーテンの価格が同じの方がわかりやすいの?
既製カーテンは巾100×丈135センチと100×178センチと100×200センチとでは金額が違いまして丈が長いほど高くなります。
当然使う生地の量が違うからです。
誰がわかりやすいって、販売する側がわかりやすいだけなんです。
「オーダーカーテンっていくらぐらいするのですか」と聞かれた時に、何窓あるかを聞いたら計算しやすいというだけなんです。考えなくてもいいというだけなんです。
よく考えてくださいよ。
販売する側は、通常品で売れば損をするような価格設定はしません。丈が240センチでも損はしない価格になっていますから丈が120センチで売れたらよく儲かるのです。
売る側が儲かるという事は、買う側にとってはけっしてお得じゃないのです。
丈の長いカーテンを買う時は低価格均一ショップで買うのはお買い得ですが、
腰窓がたくさんある場合はけっして安くはないのです。
大手メーカーでも、1,5倍使いで形態安定加工付き(ソフトウエーブ)で幅200×丈200センチでエンドユーザー向け価格が10000円としているのですが、
地域や大手得意先によって丈の価格設定が違っていて、関西向け価格設定は丈がいくらでも同じ価格になっています。
これってエンドユーザーの方を向いていないんじゃないの?
私どもの新店舗ではエンドユーザーの立場になって価格設定をします。
ブログのトップへ