12日13日と東京に行ってました。
インテリア業界の重鎮お二人と情報交換し、同業者3社のお店にお伺いして勉強させていただきました。テレビ出演のお話もありましてその打ち合わせもしてきました。すごく充実した2日間でした。
以前にもブログで書いていますが、東京に着くと思う事で、エスカレーターに乗っているときに急がない人は左側に立つのが徹底されているのに感心するのです。
大阪は逆で右側に立ちます。これは東京と大阪の文化の違いで、東京は武士文化、大阪は商人文化によるものであると私は思っていました。ここをお読みください。
https://blog.curtainkyaku.com/7969972.html
名古屋も最近は徹底されていて、東京と同じように左側に立ちます。
そしたら、その境目はどこなのかという興味がわきまして、天下分け目は関ヶ原あたりかなと思っていたら、京都はどちらかというと東京と同じ左側に立つ傾向があるのです。
駅ビルに伊勢丹が入ったからなんです。 そうどすえ。
ほんまかいな?
岡山、広島や福岡はどうなのか知らないのですが、仙台は大阪と同じ右側に立つそうです。
あまり文化は関係ないようで、大阪は万博に時に動く歩道ができ、その時に国際的に慣習とされている、急ぐ人のために左側を空けて右側に立つという事が実施されたようです。
その後、阪急梅田駅に動く歩道でも、急ぐ人のために左側を空けるようにアナウンスされ、それが習慣でエスカレーターも急がない人は右側に立つようになったようです。
大阪以外では、左側に立つようになったのはなぜかはよくわかりません。
今回、東京に行って感じたことは、電車がほとんどバケットシートになっていて、7人掛けのシートには7人がぎゅうぎゅう詰めで座っているのです。
バケットシート(写真)とは、一人ずつが隙間なく座れるようにお尻がうまく納まるような凹みのあるシートです。また、7人シートには2+3+2にわかれるように仕切りパイプがあるのです。
私が感心したのは、東京では隙間なくきれいに座っておられるのです。
大阪の電車はフラットなベンチシートタイプが多くて、7人掛けシートでも少しずつ微妙に隙間をあけて6人掛けされているケースが多いのです。
大阪の電車は、フラットなシートが多いと思います。凹みがあると、
きちっと座っていないので、凸の部分にお尻が当たる場合もあるのです。
こんな場合はお尻が痛くて赤くなるので、大阪の人は嫌うのだと思います。
そんなん知りまっか?(尻真っ赤)
今日の現場。
木製ブラインドの操作コードを取り替えました。
10年近く使って頂いていて、コードは切れていませんがヒゲがいっぱいはえて操作が重くなっていました。
(写真はクリックで拡大) 右の写真の左が今までの操作コード、右が新品。
こうしたコード類は消耗品ですので寿命があります。
スムーズにいかなくなったら早めに購入店にご連絡しましょう。
安心できるお店で購入しましょう。
ブログのトップへ





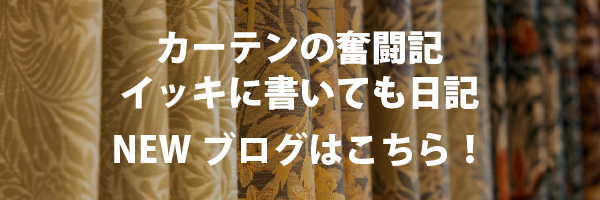
コメント